

神崎 宣武氏
五節供―端午について
端午の節供と菖蒲
端午の節供といえば、鯉のぼりや兜飾りを連想するであろう。だが、それが流行(はや)りだしたのは、江戸の町からで、全国的に広まるのは、さらにのちの近代以降のことである。『東都歳事記』にも、「紙にて鯉の形をつくり、竹の先につけて、幟と共に立る事、是も近世のならはし也」とある。そして、「出世の魚といへる諺により、男兒(だんじ)を祝するの意なるべし」と記されている。
端午の節供のもっとも古儀を伝えるのはショウブ(菖蒲)である。
たとえば、ショウブをヨモギとともに軒に刺す。それは、火ぶせ(火除け)のまじない。あるいは、虫除けのまじないとされた。総じて、魔除けのまじないである。
ショウブに勝る旬の霊力はないだろう。ショウブは、もともとにおいが強く蛇や虫をよせつけなかったことから、呪力の強い植物とされた。また、刀剣に見立てられるところから、そうされたのだ。

菖蒲湯や菖蒲酒も、またしかり。菖蒲湯のような薬湯への入浴習俗は、きわめて日本的な発達といえる。ほかにも、冬至の柚子(ゆず)湯が今日にも伝わることは、周知のとおりである。現在、種々の入浴剤が売られているのも、温泉浴の習俗の影響もあろうが、その伝統があってのことだろう。薬効もあるものの、「まじない湯」というのがふさわしい。
菖蒲酒は、ショウブの葉を細かく刻んで酒に浮かべたもの。菖蒲酒を飲む習慣は、現在ではほとんど廃れてしまったが、半世紀も前までは、栃木県下や岐阜県下、広島県下などに伝わっていた、という報告例がある。
桃の酒と同じように、菖蒲酒も忘れられて久しい。
五節供―七夕について
七夕は、五節供のうちのひとつである。節季(せっき)祝いとして中国から伝来した。
今日、七夕というと、天の川をはさんで離れ離れになっている牽牛(けんぎゅう)星<彦星>と織女(しょくじょ)星<織姫>が一年に一度だけ再会できる日、とされているが、これは、中国の、「乞巧奠」(きっこうでん)にちなんだものである。中国では、牽牛星は農業の時季を知らせる星、織女星は養蚕や針仕事をつかさどる星、とされていた。この二つの星の恋物語が誕生したのは、古く1世紀のころといわれる。
牛飼いの牽牛と機織(はたおり)の織女は恋人同士だったが、二人とも働かずに遊び暮らすようになったため、天の神様は、懲らしめに二人の仲を引き裂き、天の川の両端に置いてしまう。ところが、二人の嘆き悲しむ様子をみて、さすがにかわいそうになり、7月7日の夜にだけ、カササギ(鳥)を並べて橋をつくり、二人を会わせてあげることにした、という話である。
こうした物語は、すでに奈良時代に日本に伝えられ、当時の貴族の女性たちは、とくに織姫にちなんで技芸の上達を星に祈った、という。室町時代になると、天皇や臣下の歌札(短冊)をカジ(梶)の木に結びつけ、硯・墨・筆を飾り七遊びを行なうようになった。七遊びとは、歌・鞠(まり)・碁(ご)・花・貝覆(かいおおい)・楊弓(ようきゅう)・香(こう)である。さらに、江戸時代には、天皇がイモの葉の露で摺った墨でカジの葉7枚に一首ずつ書き、その葉で索餅を包んで屋根に投げ上げるという行事がみられるようになる。また、江戸城の大奥では、奥女中たちが歌を色紙や短冊に書いて葉竹に結び、供物とともに品川の海に流すのが定例となった。
それが、さほどに間をおかず、江戸市中にも伝わる。『東都歳事記』や『絵本江戸風俗往来』には、「短冊竹」が立ち並ぶ風景が描かれている。このところで、歌でなく願いごとを短冊に書くようになったのである。
一方、民間では、この七夕節(節供)にそれぞれの土地で固有の習俗が派生して伝わる。
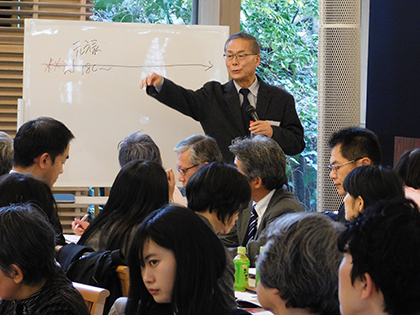
いうまでもなく、旧暦7月は、「盆」の行事を執り行なう月。祖霊を迎えて祀る盆行事の中心は15日だが、そのはじまりは1日とされ、「釜蓋朔日」(かまぶたついたち)などといった。
とくに、祖霊まつり(7月15日)の前7日間は、厳重な物忌(ものいみ)をしなければならない。7月7日は、そのかかりの日で穢(けが)れや厄災を祓(はら)う禊(みそぎ)の日という考え方が庶民社会には強く根づいていたのである。
そこでの七夕は、盆行事の一環としての性格をもつ。ところによってはナヌカビとかナヌカボン、あるいはボンハジメなどとも称される。そして、その日、墓掃除や仏壇の道具を清めることなどが広く習慣化されたのだ。
ネンブリナガシ・ネブタナガシ・ネムタナガシ・ネブトナガシなどという呼称も全国的に分布している。それらの語源は、「ねむり」(睡魔)であろう、と民俗学の先駆者である柳田國男は指摘した(論考「眠流し考」)。そして、多くの土地の伝承から、それはネム(合歓)の木で象徴され、ネムの木流しを行なったのがはじまりだったであろう、という。古い七夕流しのかたち。穢れ、あるいは邪気を、ネムの木、ネムの葉に託して流すのである。
ところで、このネブタ流しは、人形(ひとがた)流しにも、また、燈籠(とうろう)流し<燈籠送り>にも通じる。さらに、その燈籠流しが大規模に遊戯化したのが、秋田の竿灯(かんとう)であり青森のネブタである。とくに、ネブタは、その呼称からしてもネブタ流しに原型があることは明らかである。
七夕は、他の節供のように、節供料理と云うほどの定型化がみられない。その理由として、旬の食材が不足するうえに、保存もききにくい時季であることが考えられる。
たとえば、他の節供には薬酒に見立てた酒がつきものである。人日(じんじつ)(本来は1月1日、便宜的に1月7日)には屠蘇(とそ)酒、上巳(じょうし)(3月3日)には桃の酒、端午(たんご)(5月5日)には菖蒲(しょうぶ)の酒、重陽(ちょうよう)(9月9日)には菊の酒。七夕にだけそれに相当する酒がない。これも、日本特有の夏場の高温多湿の気候が、酒をつくっても保存するのにまことに不適当だったからであろう。
オトタナ(乙棚)とかオトタナバタ(乙棚桟)という仮設の棚に供えものをする習慣も伝わる。そこでの供えものは、ナスやキュウリやトウモロコシなど夏野菜といわれるものである。ここにも、盆棚との混同がみられるが、食材やその保存が限定されるこの時期を考えると、いずれも夏野菜に頼らざるをえなかったのが道理、といえよう。
江戸・東京を中心に五目飯を食べて七夕を祝う習慣もみられた。これも、かぎられた食材を炊きあわせて無難に共食するため、とみるべきである。
